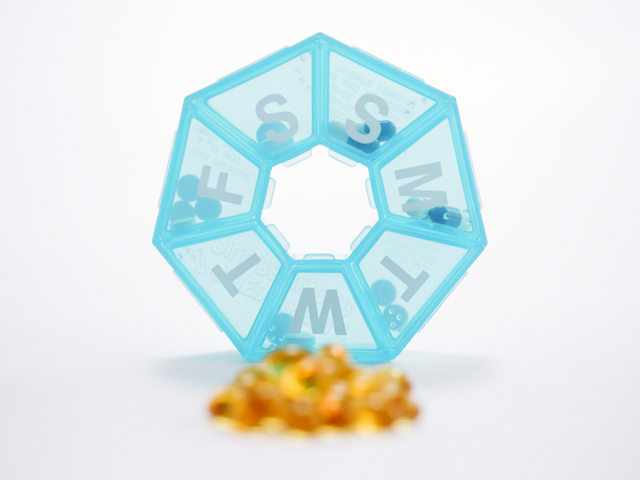専門看護師とは
専門看護師とは複雑な状況での疾患があり、介護が非常に難しい状況の家庭などに対して専門知識を持って高い水準の介護を行う人です。専門看護師は専門性に優れた看護の知識、対処方法を持ちあわせて、介護が必要な患者およびその家族のためにその力を発揮します。
専門看護師は大きく分けて6つの役割を果たします。専門看護師はその高い専門性を患者の家族および集団に対して実践します。そして2つ目に看護を必要とする人および在宅や施設でのケア提供者に対してより良い介護を行うためのコンサルティングを行います。3つ目に必要なケアが患者に対して円滑に行われるように、医療福祉に関連する人に対してコーディネートを行います。次に4つ目として、患者およびケアを行う人、個人及び集団においてその権利を守るため、倫理的な問題の解決および葛藤に対するヒアリングと解決に努力します。5つ目については今後の専門看護も含めて技術および満足度の向上を目指すため教育的役割を果たします。最後に6つ目、専門看護師として専門看護の現場においてより良い看護を目指すために、ケア対象者に研究を実践します。この大きく分けた6つの事項について日々その技術向上のために切磋琢磨します。
専門看護の対象
では専門看護の対象となる疾患について、どのようなものがあげられるのでしょうか。一例で上げるとまずガンがあげられます。ガンは看護のために特殊な投薬や治療が必要になります。またガン患者特有の不安要素などもあるので、患者に特化したケアを行う必要があります。次に精神疾患者に関しても通常のケアとは異なるケアを行う必要があります。精神疾患の場合は四肢は十分に使えますが、通常できることができなくなったり、心理的に不安になると良くないので、心のケアを中心的に行う必要があります。また在宅看護や老人看護も専門看護師として専門性を持ちあわせて対応しなければいけない看護の一つですね。
この専門対象は申請の上で都度認定を行い、認定された場合に専門看護の対象となります。時代が変わるに従い、これまで少数派だった疾患が多数となったり、特別なケアが必要であるという判断がくだされるケースもあるので、日々その対象となる疾患には変化があると言ってもいいでしょう。
専門看護師になるには看護師の免許を取得した上で所定の単位を習得している事、また看護の実務が5年以上あることが必要とされています。その上で審査されて晴れて専門看護師となることができるのです。