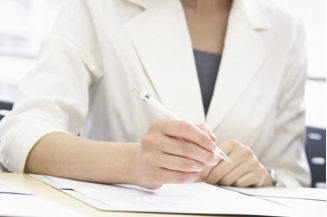精神障害者をサポートするエキスパート

精神保健福祉士とは、精神医学ソーシャルワーカーとも呼ばれていて、精神障害者を専門にケアする仕事です。
といっても、治療に携わるのではなく、精神障害者の方とその家族が適切な支援を受けられるように、制度面での助けを与えるとともに、自立した生活を送れるように、生活上のアドバイスなどを与えることになります。
実際の仕事場としては、メンタルクリニックや病院の精神科などの医療機関が挙げられます。
障害者認定を受けるための手続きを行ったり、入院手続きを進めたりします。
精神障害による入院には、通常の身体的病気の入院とは異なる手順が生じることもありますので、精神保健福祉士の働きは重要です。
というのも、精神障害者が入院を必要とされると客観的に判断されていても、本人が拒否するというケースも多々ありますので、保護的な措置として入院をしてもらうことが必要になります。
周囲の安全確保や本人の人権など、複雑な要素が絡み合っていることが多いので、プロの目から適切な手続きができるように、精神保健福祉士がスムーズに入院措置を進めていくのです。
こうした入院に関する手続きが、病院における主な仕事となるでしょう。
生活の質を向上させる手伝いをする
また、精神保健福祉士は、精神障害者本人とその家族の相談に乗って、生活の質を向上させるための手助けをするという重要な仕事もあります。
それぞれの必要や事情に合った適切な病院や、公的サービスを紹介したり、その後の流れを確認して、しっかりとサポートが機能を果たしているかなどを確認することもあります。
また、社会復帰することが治療、公的サービスの目的ですので、治療の段階に応じて、就職に関する相談に乗ったりすることもあります。
総合的なサポートを通して、精神障害者が自立できるように助けているのです。
精神保健福祉士の資格を取る
こうした業務の多くは、資格がなくてもできるものですので、特に精神保健福祉士の資格を取らないといけないわけではありません。
しかし、現実的には有資格者を応募の条件としている病院などが多いので、資格を持っているのは大きなアドバンテージとなるでしょう。
この国家資格を取るには、福祉系の大学を卒業しているなどの、学歴による条件が付されています。
福祉系の短大を卒業してから実務経験を積むことで、国家試験の受験資格を得られるというパターンもありますので、無理なく資格を取れる道を探ってみると良いでしょう。
ニーズが高く、精神保健の重要性が大きくなっていますので、有資格者の需要は大きくなっていくと考えられています。
興味のある方は、受験資格に関する詳しい情報などをチェックしてみると良いでしょう。